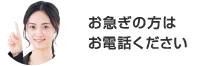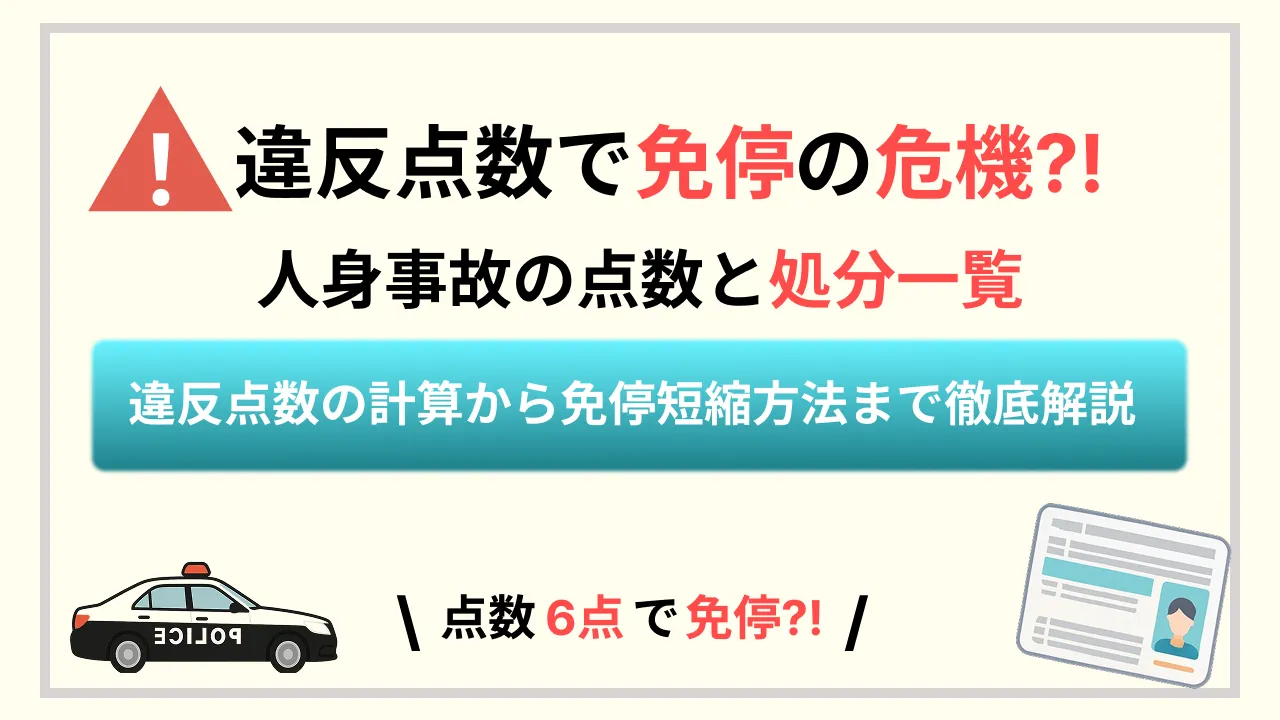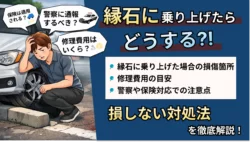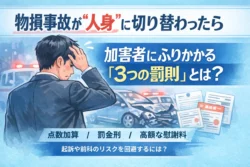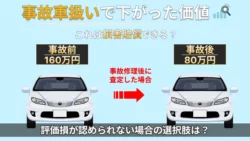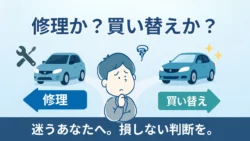車の事故というのは、突如として発生してしまうもの。
パニックになりながらも、頭の中によぎるのは事故発生後のペナルティです。
「相手に怪我を負わせてしまった場合、どんな責任を負う…?」
「1年前にも事故を起こしてるからもしかして免停…?」
など、交通事故で人的被害を出した場合の責任や免許停止処分について不安を覚える方も少なくないことでしょう。
今回は人身事故を起こした場合の違反点数や罰則についてくわしく紹介します。
また、
- 免許が制限される点数の基準
- 免許停止期間を短縮する方法
- 検察庁に呼び出しを受けた場合の流れ
- 人身事故を起こした場合の民事責任
なども解説します。
違反行為をしてしまった後の行動が違反点数や損害賠償金にも繋がるため大切となります。
ぜひご自身の状況と照らし合わせて参考にしていただければ幸いです。
 岩淵 俊
岩淵 俊
中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む
人身事故で加算される違反点数と交通事故の罰金
人身事故では加害者に対して行政処分として「違反点数」が科されます。
違反点数は、事故の内容と責任の重さによって加算され、以下の点数の合計で判断されます。
- 運転中の違反行為に対して定められた「基礎点数」
- 事故の被害状況に応じた「付加点数」
主な交通違反ごとの基礎点数は以下のとおりです。
| 名目 | 点数 | 反則金 | |
| 安全運転義務違反(よそ見・わき見運転) | 2点 | 9千円 | |
|---|---|---|---|
| 交差点安全進行義務違反(交差点内の前方不注意・安全不確認) | 2点 | 9千円 | |
| スピード違反 | 1~12点 | 9千~3万5千円 | |
| 無保険運行 | 6点 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
| 酒気帯び運転 | 13~25点 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
| 無免許運転 | 25点 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
| ※危険防止措置義務違反(当て逃げ) | 5点 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 | |
| ※救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
人身事故が発生すると、基礎点数は一般的に「安全運転義務違反」(2点)が適用されます。
なお、複数の違反を同時に行った場合は、最も点数の高い違反の基礎点数だけが適用されます。
スピード違反や無免許運転などに該当する場合は、重い違反の点数が適用されます。
ただし、当て逃げやひき逃げは別途重大な違反と判断され、点数が上乗せされます。(参考:警視庁)
また、反則金はスピード違反のように同じ違反でも程度により点数や反則金が大きく異なりますので、軽視できません。
なお、人身事故の場合は被害の深刻度に応じて付加点数が加算されます。
付加点数は、加害者の責任の重さ(過失の程度)と、被害者のけがの状態によって基礎点数に上乗せされる点数のことです。
交通事故で人的被害が発生した場合の付加点数と罰金額は以下のとおりです。
| 怪我の程度 | 加害者の過失が大きい | 被害者にも過失がある | 罰金額相場 |
| 相手が死亡した | 20点 | 13点 | 50万円~100万(※) |
|---|---|---|---|
| 治療期間が3ヶ月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 | 30万円~50万円(※) |
| 治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 | 20万円~50万円 |
| 治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | 15万円~30万円 |
| 治療期間が15日未満 | 3点 | 2点 | 10万円~20万円 |
※罰金刑ではなく、拘禁刑が言い渡される場合もある
付加点数は被害の程度が重いほど加算される点数も大きくなります。
特に加害者の不注意による死亡事故では、一度に20点が加算されるため、免許取り消しがほぼ確実になります。
また、「加害者の不注意による事故」の場合は点数が重く、「被害者にも過失がある」ケースでは点数が軽減されます。
違反点数を計算する方法は、上記で紹介した基礎点数と付加点数に合わせて過去3年以内の違反行為の累積点数の合計です。
例えば半年前にスピード違反を犯している状態で、被害者の飛び出しによる軽度の人身事故(治療15日未満)が発生した場合は、違反点数が5点になります。
点数の内訳は下記のとおりです。
- 累積点数:スピード違反(1点)
- 基礎点数:安全運転義務違反(2点)
- 付加点数:治療期間が15日未満の事故(2点)
累積点数が分からない方は、免許センターの窓口やWEBで累積点数等証明書を取得することで調べられます。
取得方法について詳しくは「累積点数の確認方法と累積点数通知書遅延時の対処法」で解説します。
なお、事故を起こした後の流れに関しては下記の記事をご確認ください。

交通事故の違反点数が6点以上だと免許が制限される
人身事故により加算される違反点数が6点を超えると、免許停止や免許取り消しといった行政処分を受けることになります。
行政処分は、過去3年間の間に受けた免許停止処分や取消処分の回数(前歴)と今回の交通違反によって加算された点数に基づいて決定されます。
「前歴」は行政処分を受けるたびに回数が累積され、行政処分を受けた日から3年間行政処分を受けなければ加算された前歴はリセットされるという仕組みです。
なお、前歴の数が増えるごとに行政処分の基準点数は厳しくなります。
前歴0回の場合は6点以上ですが、前歴1回で4点以上、前歴2回あると2点で免許停止になります。
| 前歴(過去3年間の行政処分) | 行政処分の基準点数 |
| 0回 | 6点以上 |
|---|---|
| 1回 | 4点以上 |
| 2回 | 2点以上 |
前歴0回の場合の行政処分の具体的な制限は下記のとおりです。
| 処分 | 違反点数 | 日数 |
| 免許停止 | 過去3年間で累積点数が6点以上 | 30日~90日 |
|---|---|---|
| 免許取り消し | 過去3年間で累積点数が15点以上 | 1年~5年 |
前述したとおり、免許停止や取消の判断は、警察庁の定める累積点数制度に基づいて行われます。
例えば、歩行者との接触事故で相手に全治1ヶ月の怪我を負わせた場合は、過去3年間無事故・無違反を維持していても、30日間の免許停止処分をうけることになります。
安全運転義務違反(2点)+怪我による付加点数(6点)=8点
※付加点数の考え方は、「人身事故で加算される違反点数」の表に基づく
これに、過去の違反点数が加算されたり、速度超過や酒気帯び運転など基礎点数が重い違反が適用されたりすると、1年間の免許取り消しになることもあります。
違反点数ごとの詳しい行政処分は、警視庁の行政処分基準点数をご確認ください。
なお、最後の違反から1年間無事故・無違反の場合は、今回の事故による点数のみで処分が決まります。
累積点数の確認方法と累積点数通知書遅延時の対処法
人身事故を起こすと1週間~4週間以内に「累積点数通知書」が届きます。
これは、累積された過去3年間の違反点数を知らせるもので、6点以上の場合は免許停止処分を受けることが確定します。
重要なのは、「通知が来ない=セーフ」ではないという点です。
通知の有無に関わらず、すでに行政処分の対象になっているケースもあるため、通知書が届いているかどうかで判断せず、自分で点数を調べることが重要です。
累積点数通知書がなかなか届かない場合は、自分の点数や違反歴を「運転記録証明書」または「累積点数等証明書」で自分の点数や違反歴を確認しましょう。
累積点数等証明書の取得方法は以下の通りです。
| 場所 | 手続き方法 | 発行までの日数 |
| 免許センター | 窓口にて申請 | 2~3日/郵送:1週間程度 |
|---|---|---|
| 郵便局 | 警察署で経歴証明申込用紙を貰ったあと、窓口で申し込み | 10日~2週間 |
| WEB | アプリから申し込み | 支払いから10日程度 |
必要なものとしては、運転免許証、申請書、発行手数料(670円)の3点です。
もし、郵便局で申し込む場合は、振込手数料が別途必要になります。
また、代理申請する場合は委任状と代理人の身分証が必要になります。
免許センター以外の方法で発行する場合は、最低でも1週間かかります。
お急ぎの方は、免許センターの窓口で手続きを行いましょう。
取得した証明書は弁護士との相談時や保険会社とのやりとりでも資料として使えます。
違反点数はいつリセットされる?違反歴別の条件
ここまでは引かれる違反点数や人身事故で負う必要がある処分などを紹介してきました。
では、実際に免許の点数が引かれた場合、リセットされる時期はいつなのか紹介していきます。
基本的に違反点数は、過去3年間の違反行為による点数が累積されます。
違反点数をリセットするには、大きく3つの方法があります。
| リセット条件 | 説明 |
| 1年間の無事故・無違反 | 最後の違反から1年経過ですべて0点にリセット |
|---|---|
| 2年間の無事故・無違反 | 最後の違反から2年経過した後に3点以下の軽微な違反をした場合、違反後3カ月以上無事故・無違反で経過すると0点にリセット |
| 行政処分を受けた | 過去3年間に行政処分を受けた場合、処分を受けた日を起点として0点にリセット |
表からわかる通り、行政処分を受けた場合を除いて違反点数のリセットは「無事故・無違反の継続が絶対条件」です。
なお、点数がリセットされても違反歴は消えず、「運転経歴証明書」には過去の違反や処分歴が記録として残ります。
過去の違反履歴や点数がいつ消えるか不安な場合には、自動車安全運転センターもしくはWEBで運転記録証明書を発行して確認しましょう。(手数料として670円必要)
次の章では、免許停止処分を受けた場合に期間を短縮する方法をお伝えします。
免停期間を短くする「停止処分者講習」の活用
免許停止処分を受けた場合、以下の停止処分者講習を教習所などで受けることで、免許停止期間を短縮できます。
- 短期講習:30日の免許停止処分者対象
- 中期講習:60日の免許停止処分者対象
- 長期講習:90日以上の免許停止処分者対象
停止処分者講習は、該当の講習を受けることで免停期間を最大で約半分まで短くすることが可能です。
ただし、停止処分者講習を受けたからといって必ず短縮されるわけではなく、講習の最後に受ける試験の成績によって、短縮される日数が決まります。
たとえば、免停30日の短期講習において試験の成績が「優」であれば、たった1日で免停期間が終わります。
試験で良い成績を取るためには、交通ルールや安全運転に関する知識をしっかりと学び直す必要があるので、真剣に講習内容に取り組むことが極めて重要です。
なお、「違反者講習(3点以下の交通違反の繰り返しで違反点数が6点に達した人の免許停止処分を回避する制度)」と混同しやすいので注意しましょう。
講習時に持参するものは以下の通りです。
- 運転免許証停止処分書:免停処分を受けた際に交付される重要な書類
- 印鑑(認印推奨):手続きや書類への押印に使用
- 受講申請書:事前に記入して持参するか、会場で記入
- 筆記用具:講習中のメモや試験に使用
- 講習料金:現金で支払う場合が多い
特に運転免許証停止処分書は、講習を受ける資格があることを証明する書類であるため、絶対に忘れないようにしましょう。
受講申請書は教習所によって事前配布している場合もあるので、申し込み時に確認しておくと良いでしょう。
停止処分者講習は受けなくても問題はありません。
ただし、免停期間を大幅に短縮できる可能性があるため、運転を早く再開したい方にとっては、受講を検討する価値のある制度です。
では、詳しく紹介していきます。
【免停30日の人】短期講習
短期講習は、違反点数が6~8点で30日の免許停止処分を受けた人だけが受講できる講習です。
講習料金は約12,600円かかりますが、最大で29日間短縮されますので、実質免停期間を1日にすることが可能です。(免許停止処分歴は加味される)
免停講習の目的は、違反行為の反省と、再発防止です。
短縮日数は講習後の試験の結果で決まります。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 29日間の短縮 |
| 成績「良」 | 25日間の短縮 |
| 成績「可」 | 20日間の短縮 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 短縮なし(30日免許停止) |
※講習料金:約12,600円 受講時間:1日(6時間)
成績が「優」となるためには、交通ルールを正確に理解していることはもちろん、安全運転に対する深い認識が必要です。
講習内容は、短期講習で行われる代表的な講習内容は以下の通りです。
- 教本を使った座学講義:交通ルールの詳細解説と事故事例の分析
- 適性検査と診断:運転に関する心理的特性や反応能力の測定
- 統計データの学習:事故の発生状況や違反の傾向分析
- グループディスカッション:他の受講者との意見交換と気づきの共有
試験では、標識の意味や速度制限、追い越しのルール、駐車・停車に関する規則など、基本的な交通法規に加え、事故を防ぐための実践的な知識が問われます。
もし試験で20点以下、または正答率が50%未満だと「不可」となり、せっかく講習を受けても期間短縮の恩恵を受けられないため、決して油断はできません。
この講習は単に知識を詰め込むだけでなく、あなたがなぜ違反を犯してしまったのか、そして今後どうすれば再発を防げるのかを深く考えるための貴重な機会となります。
次の章では、より免停期間が長い「中期講習」について詳しく解説していきます。
【免停60日の人】中期講習
中期講習は、違反点数が9〜11点で60日の免許停止処分を受けた人を対象とした講習です。
講習料金は約21,000円かかりますが、最大で30日停止期間を短縮できます。
基本的な流れは、短期講習と変わりませんが、中期講習は2日間にわたって合計10時間行われます。
短期講習と比べてより深く、そして実践的な安全運転について学びます。
中期講習の免停期間の短縮日数は以下のとおりです。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 30日 |
| 成績「良」 | 27日 |
| 成績「可」 | 24日 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 短縮なし(60日免許停止) |
※講習料金:約21,000円 受講時間:2日連続(10時間)
中期講習で行われる代表的な講習内容は以下の通りです。
- 教材を使った講義:交通法規の詳細解説と違反事例の分析
- ビデオを使った講義:実際の事故映像や危険場面の視覚的学習
- 適性検査:運転能力や性格特性の詳細な分析
- シミュレーターによる模擬運転:危険回避や安全運転技術の実践練習
- 交通法に関する座学:法改正内容や最新の交通情勢
- 運転技能に関する座学:車両特性や運転技術の理論学習
中期講習の大きな特徴は、座学だけでなくシミュレーターを使った模擬運転が、カリキュラムに含まれている点です。
実際の運転席に近い環境で、急ブレーキが必要な場面や見通しの悪い交差点での判断、悪天候時の運転など、様々な危険な状況を安全に体験できます。
また、ビデオ講義では実際の交通事故の映像を見ることで、あなたの違反行為がどのような悲劇的な結果を招く可能性があるのかを視覚的に理解することができます。
これらの実践的な学習を通じて、交通ルールが単なる規則ではなく、命を守るための大切な約束事であることを深く心に刻むことができるでしょう。
この講習は、あなたが運転者としての責任感を再認識し、安全に対する意識を総合的に高めるための貴重な機会となります。
次の章では、さらに重い免停処分を受けた方向けの「長期講習」について詳しく見ていきましょう。
【免停90日以上の人】長期講習
長期講習は、違反点数が12〜14点で90日以上の免許停止処分を受けた人を対象とした講習です。
講習料金は約28,000円かかりますが、最大で45日停止期間を短縮することができます。
この処分を受ける方は、重大な違反を犯したか、あるいは短期間に何度も違反を繰り返してしまったケースがほとんどです。
単に交通ルールを覚えるだけでなく、運転に対する考え方を根本から変えることが求められ、他の講習に比べて短縮日数や講習時間が大きく異なります。
長期講習の免停期間の短縮日数は以下のとおりです。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 45日 |
| 成績「良」 | 40日 |
| 成績「可」 | 35日 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 短縮なし(90日免許停止) |
※講習料金:約28,000円 受講時間:2日連続(12時間)
講習内容は中期講習とほとんど同じですが、各項目により多くの時間を割いて深く学習します。
- より詳細な事故分析:重大事故の原因と防止策の徹底的な検証
- 個別指導の充実:受講者一人ひとりの問題点に応じた個別アドバイス
- 実践的な危険予測:様々な交通場面での危険要因の発見と対処法
- 心理的要因の分析:なぜ違反を繰り返してしまうのかの深層心理の探求
なお、長期講習の受講は、免許停止日数の半分が経過するまでしか受講できません。
具体的には、免停90日の場合は45日経過までが受講できる期限となります。
2日間にわたる長時間講習のため、処分通知を受け取ったらご自身の予定を加味したうえで、早急に受講することをおすすめします。
交通事故で科される刑事処分
交通事故で相手にけがをさせた場合、行政処分(違反点数の加算や免許停止)だけでなく、刑事処分を受ける可能性があります。
刑事処分とは、事故によって発生した「犯罪行為」に対して科される罰のことで、加害者の過失の程度や事故の深刻さに応じて内容が変わります。
主な刑事罰には、「拘禁刑」と「罰金刑」の2種類があります。
- 「拘禁刑」とは、2025年6月から「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化して新設された制度で、刑務所での作業や更生プログラムが課される場合もあります。
- 「罰金刑」は裁判所に定められた金額(1万円以上)を納付する処分です。
交通事故においてどの刑罰が適用されるかは、加害者の運転態度や事故の内容によって異なります。
代表的な罪名と内容を以下にまとめました。
| 罪状 | 内容一例 | 刑罰 |
| 過失運転致死傷罪 | 注意不足や不注意で起こした人身事故 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下罰金 |
|---|---|---|
| 危険運転致死傷罪 | 飲酒や無免許運転など悪質な運転行為による事故 | 死亡:懲役1年以上20年以下/負傷:懲役15年以下 |
| 殺人罪(※未必の故意を含む) | 故意やそれに近い強い悪意が認められる事故 | 無期または懲役5年以上 |
最も一般的なのは、「過失運転致死傷罪」です。
これは、わき見運転や安全不確認といった注意義務違反に該当する事故で適用されます。
一方、酒気帯びや薬物使用、無免許など悪質性の高い運転で相手を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」に問われます。
平成26年に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」により処罰が厳格化され、最長20年の懲役が科される可能性があります。
さらに深刻なケースとして、「未必の故意」が認められた場合には「殺人罪」に問われる可能性もあります。
これは、「事故になるかもしれない」とわかっていながら運転を続けたような心理状態を指し、悪質性が極めて高いと判断された場合に適用されます。
このように、交通事故の刑事処分は加害者の行為や事故の状況によって大きく異なります。
次の章では、こうした処分がどのような流れで決定されていくのかについて解説します。
警察の取調べから刑事処分が決まるまでの流れ
交通事故で人的被害を出した場合に届く出頭通知書は、「刑事処分が確定した」という意味ではありません。
出頭通知書は、多くの場合、警察が事実関係を確認し、供述調書を作成するための任意出頭の要請です。
最終的な処分は、警察からの捜査結果(書類送検)を受けた検察官が、あなたの供述内容や事故の状況を踏まえて判断します。
検察官が下す判断は以下の3つです。
- 罰則を受けない「不起訴」
- 裁判なしで罰金を支払う「略式罰金」
- 正式な裁判を受ける「公判請求」
どの処分になるかは、取調べでの供述内容が大きく影響するため、落ち着いて正確に事実を伝えることが重要です。
なお、交通事故後の刑事処分の流れは次のように進みます。

上記の流れは、警察庁および法務省が公表している刑事手続きの一般的な仕組みに基づくものです。
事故の内容が軽微で、被害者が軽傷の場合は「略式罰金」で終わることが多くなります。
一方、事故が重大な場合や悪質性が高いと判断された場合は「正式裁判」となり、拘禁刑などのより重い刑罰が科される可能性もあります。
しかし、すべてのケースで罰則が科されるわけではありません。
検察官は事故状況や加害者の運転態度、反省の様子、被害者の処罰感情など、さまざまな要素を総合的に評価したうえで、起訴便宜主義という裁量によって最終判断を下します。
つまり、交通事故後に検察庁に呼び出されたからといって、必ず罰金や刑罰が科されるとは限らないのです。
では、具体的にどのような場合に不起訴となり、罰金なしで済む可能性があるのでしょうか。
続いては検察庁に呼び出された後でも罰金が科されずに済む代表的なケースについて解説します。
交通事故後に検察庁に呼び出されても罰金なしで済むケース
交通事故で人的被害を出して検察庁から呼び出しを受けても、検察官の判断によっては不起訴処分となり、罰金も前科もつかずに手続きが終了することがあります。
不起訴処分となる可能性が高い代表的なケースは次の通りです。
- 被害者の怪我が打撲や擦り傷で、加害者の一時的な不注意による事故の場合
- 示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を示した場合
- 初犯で反省の態度が明確である場合
- 信号無視や急な飛び出しなど被害者側にも一定の過失がある場合
こうした条件を満たしていると、検察官は「起訴して裁判にかけるほどの悪質性がない」と判断し、不起訴処分となる可能性があります。
特に示談の成立は、検察官の判断に大きな影響を与えるため、事故後は被害者への誠実な対応を心がけることが非常に重要です。
ただし、人身事故の示談交渉は個人で進めるのが難しいケースも多く、感情的なもつれから交渉がうまくいかないこともあります。
例えば、被害者の通院期間の延長や、後遺障害等級関連で揉めるケースが多いです。
示談交渉期間について詳しくは下記の記事をご確認ください。

また、検察官との取調べでどのように対応すべきか不安を感じる方も多いでしょう。
そのような場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は示談交渉を代行してくれるだけでなく、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出するなど、不起訴処分の可能性を高めるためのサポートをしてくれます。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。
次の章では、交通事故で民事責任を負った場合の損害賠償について、詳しく見ていきましょう。
交通事故で民事責任を負った場合の損害賠償
人身事故を起こすと、刑事処分とは別に民事処分として被害者の損害に応じた損害賠償を支払うことがあります。
ここで言う損害とは、負傷・死亡させてしまった人物に対する損害や、車などを損壊させたことに対する損害を指します。
被害者に後遺障害が残った場合は、賠償金額が高くなる傾向にあります。
賠償金は「自動車損害賠償保障法」や「民法」によって義務付けられており、後遺障害が認定された場合には高額になる傾向があります。
民事処分によって支払う損害賠償金の具体例は以下のとおりです。
| 賠償項目 | 内容例 |
| 治療費 | 通院費、入院費、薬代など実際の医療費 |
|---|---|
| 修理費 | 車やバイクなど壊れた物の修理・買い替え費用 |
| 逸失利益 | 怪我がなければ得られた収入 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛への補償 |
| 介護費・付添看護費 | 重度の後遺障害で介助が必要な場合の費用 |
事故を起こして民事処分を受けた場合、運転者は自賠責保険によって損害賠償の一部を支払えますが、足りない分は任意保険による保険金、もしくは実費で支払うこととなります。
負担を軽くするには、任意保険の加入内容をあらかじめ見直しておくことが重要です。
被害者から損害賠償請求を受けた場合、示談交渉で対応することが多いですが、内容に納得できない場合は弁護士に相談するのが望ましいです。
事故被害者が請求できる損害賠償に関しては、下記の記事でくわしく解説しております。

次の章では、人身事故を起こした場合によくある疑問に関して解説いたします。
よくあるケース別|加算点数と処分の目安
人身事故を起こしたときの加算点数や処分の内容は、事故の状況や過失の割合によって変わります。
免停になるか不安な方も多いですが、重要なのは自分の前歴と点数の累積状況です。
この章では、代表的な4つのケースごとにどれくらいの点数が加算されるのか、免停になる可能性があるのか、どんな対応が必要かを具体的に整理して解説します。
Q.治療15日未満で加害者に過失がある場合の点数は何点?
A.過去3年以内に無事故・無違反であれば5点加算されます。1点でも違反点数をもっている場合は、累積点数により免停になります。
Q.追突事故で過失割合が8:2の場合は免停を回避できる?
A.たとえば治療期間が30日未満のケースでは、安全運転義務違反(2点)と付加点数(4点)の6点が加算されるので、免停は回避できません。
Q.過去に免停歴がある場合、少ない点数でも処分されるの?
A.過去3年以内に免停歴があると行政処分の基準が厳しくなり、通常6点で免停のところ前歴1回の場合は4点で免停、前歴2回以上の場合は2点で免停になります。
Q.点数通知が来ないと免停じゃない?
A点数通知書が届かなくても免停になるケースはあります。通知書の発送は行政の都合によって1か月前後遅れることがあるので、少しでも不安があれば「運転記録証明書」を発行して確認しましょう。
まとめ
人身事故を起こすと、違反点数の加算や免許停止といった行政処分に加えて、罰金や懲役などの刑事処分、さらに被害者への損害賠償という民事上の責任まで負う可能性があります。
どこまでの処分になるかは、加害者の過失の程度や被害者のけがの重さ、事故後の対応によって大きく変わります。
以下に本記事の重要ポイントをまとめます。
- 人身事故の違反点数は、基礎点数+付加点数の合計で決まる
- 累積6点以上と前歴の有無に応じて免許停止・免許取消などの行政処分が科される
- 停止処分者講習を受講すれば、免停期間の短縮が可能である
- 検察庁から呼び出しを受けても、罰金なしの可能性がある
- 刑事処分の有無にかかわらず、治療費や慰謝料などの損害賠償義務がある
人身事故の加害者になってしまうと、仕事や日常生活に大きな影響が出ますが、制度や流れを正しく理解しておけば、次に取るべき行動が見えやすくなります。
違反点数や罰金、検察庁からの呼び出しについて不安が強い場合は、一人で抱え込まず、交通事故に詳しい弁護士に相談することも検討してください。
また、事故で大きく損傷した車の処分に悩んでいる方は、事故車買取のタウにご相談ください。
「タウ」では、世界120ヵ国以上に及ぶ販売ネットワークを活かし、事故車両であっても買取が可能です。
24時間、年中無休で全国から査定依頼を受付ておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 岩淵 俊
岩淵 俊
中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。