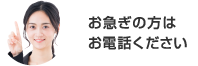車の事故というのは、突如として発生してしまうもの。
パニックになりながらも、頭の中によぎるのは事故発生後のペナルティです。
「相手に怪我を負わせてしまったけど、もしかして免停では…?」
「ちょっとした事故だけど、1年前にも同じことやってるんだよな…」
など、違反点数についてや、免停のことを考える方も少なくないことでしょう。
今回は人身事故の点数を一覧表で紹介していきます。
また、
- 免許が制限される点数
- 免許の点数がリセットされる期間
- 免停の期間を短縮する方法
なども合わせて解説していきます。
違反行為をしてしまった後の行動が違反点数や損害賠償金にも繋がるため大切となります。
ぜひご自身の状況と照らし合わせて参考にしていただければ幸いです。
 小池 一敏
小池 一敏
事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。 ...続きを読む
人身事故で加算される違反点数
人身事故では基礎点数と付加点数が合算されて違反点数になります。
基礎点数と付加点数の一覧は以下の通りです。
◆基礎点数
| 名目 | 点数 | |
| 無灯火 | 1点 | |
| 安全運転義務違反
(よそ見・わき見運転) |
2点 | |
| 交差点安全進行義務違反
(交差点内の前方不注意・安全不確認) |
2点 | |
| 追い越し違反 | 2点 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2点 | |
| スピード違反 | 1~12点 | |
| 無車検運行 | 6点 | |
| 無保険運行 | 6点 | |
| 無免許運転 | 25点 | |
◆付加点数一覧
| 交通事故の種類 | 専ら
(事故の原因が加害者の不注意である場合) |
専らではない
(被害者にも非がある場合) |
| 相手が死亡した | 20点 | 13点 |
| 治療期間が3カ月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 |
| 治療期間が30日以上~3カ月未満 | 9点 | 6点 |
| 治療期間が15日以上~30日未満の事故 | 6点 | 4点 |
| 治療期間が15日未満/建造物損壊事故 | 3点 | 2点 |
※「専ら(もっぱら)」とは、加害者(運転していた方)の不注意によって発生した事故のことを指します。
一方で「専ら以外」とは、被害者の方に過失があるケースなど、加害者の不注意の度合いが大きくないケースです。
上記の表の点数と過去3年以内の違反行為の累積点数が自分の持ち点になります。
例えば半年前にスピード違反で1点、今回の人身事故で被害者が治療期間が15日未満の場合は下記のような点数になります。
(今回は加害者の不注意で起きた事故ではなかったとします。)
| 1点(スピード違反)+2点(不注意)+2点(治療期間が15日未満の事故)=5点 |
上記の場合の持ち点は5点になります。
累積点数が分からない方は累積点数等証明書を取得して調べられます。
累積点数等証明書の取得方法は以下の通りです。
| 場所 | 手続き方法 | 発行までの日数 |
| 免許センター | 窓口にて申請 | 2~3日/郵送1~2週間 |
| 郵便局 | 警察署で経歴証明申込用紙を貰ったあと、窓口で申し込み | 10日~2週間 |
| WEB | アプリから申し込み | 支払いから10日程度 |
必要なものとしては、免許証と発行手数料(670円)になります。
早く欲しい場合は少し面倒ですが、免許センターに出向いて直接証明書を受け取りましょう。
違反点数が6点以上だと免許が制限される
加算された点数が6点以上の場合は免許が制限されます。
具体的な制限は下記の3つになります。
| 処分 | 違反点数 |
| 免許停止 | 過去3年間で累積点数が6点以上 |
| 免許取り消し | 過去3年間で累積点数が15点以上 |
| 反則金の支払い | 3,000円以上
(違反点数によって異なる) |
罰則として科される反則金は以下の通りです。
| 違反行為 | 反則金 |
| スピード違反 | 9,000~35,000円 |
| 携帯電話の使用(保持) | 12,000~25,000円 |
| 追い越し違反 | 9,000円 |
| 無灯火 | 6,000円 |
上記の他に交通違反や、交通事故をおこした前歴のあるドライバーは、より厳重な処罰となります。
3年以内に1回免停になったことがある方は、4点以上の違反で免停になり、前歴2回以上だと2点以上が免停対象となります。
免許の点数がリセットされる時期
ここまでは引かれる違反点数や人身事故で負う必要がある処分などを紹介してきました。
では、実際に免許の点数が引かれた場合、リセットされる時期はいつなのか紹介していきます。
免許の違反点数がリセットされる時期は無事故・無違反の期間がどのくらいかで決まります。
| 無事故・無違反の期間 | 説明 |
| 1年間 | 0点にリセット |
| 2年間 | 3カ月以上、無事故・無違反で経過すると0点にリセット(1~3点の違反行為に限る) |
前回、違反をした時期は運転証明書で分かります。
運転証明書は自動車安全運転センターもしくはWEBから発行可能です。
手数料として670円必要なので、用意しておきましょう。
申し込みから交付までは1〜2週間かかります。
免停期間を短くする「停止処分者講習」
ここまでは免許の点数がリセットされる条件を紹介しました。
しかし累積点数が6点になってしまい、免停になった場合は困りますよね。
免停期間は講習を受けることで短縮できます。
講習は教習所で受けることができます。
免停期間を短縮するための講習は、以下の3種類があります。
| 講習の種類 | 違反点数 | 免停の期間 | 最大短縮期間 |
| 短期講習 | 6~8点 | 30日 | 20日~29日
(成績で異なる) |
| 中期講習 | 9~11点 | 60日 | 24日~30日
(成績で異なる) |
| 長期講習 | 12~14点 | 90日 | 35日~45日
(成績で異なる) |
講習時に持参するものは以下の通りです。
- 運転免許証停止処分書
- 印鑑
- 受講申請書
- 筆記用具
- 講習料金
では、詳しく紹介していきます。
【免停30日の人】短期講習
短期講習は、30日の免停処分の人だけが受講できる講習です。
短縮日数は講習後の試験の結果で決まります。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 29日間の短縮 |
| 成績「良」 | 25日間の短縮 |
| 成績「可」 | 20日間の短縮 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 不可 |
※講習料金:約12,600円 受講時間:1日(6時間)
前歴の有無も加味されますが、最大で29日間短縮されますので、実質免停期間を1日にすることが可能です。
免停講習の目的は、違反行為の反省と、再発防止です。
講習内容は、交通ルールや安全運転の重要性、事故の統計データなど、ドライバーとしての意識や知識を高めるためにあります。
教本を使った座学講義や、機器、筆記を伴った転適性検査と診断があります。
【免停60日の人】中期講習
基本的な流れは、短期講習と変わりませんが、短縮日数は異なります。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 30日 |
| 成績「良」 | 27日 |
| 成績「可」 | 24日 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 不可 |
※講習料金:約21,000円 受講時間:2日連続(10時間)
中期講習で行われる代表的な講習内容は以下の通りです。
- 教材を使った講義
- ビデオを使った講義
- 適性検査
- シミュレーターによる模擬運転
- 交通法に関する座学
- 運転技能に関する座学
【免停90日以上の人】長期講習
長期講習の場合も、短縮日数、講習料金、講習時間が上記の2つと異なります。
| 成績 | 短縮日数 |
| 成績「優」 | 45日 |
| 成績「良」 | 40日 |
| 成績「可」 | 35日 |
| 点数が20点以下で、正答率50%未満 | 不可 |
※講習料金:約28,000円 受講時間:2日連続(12時間)
講習内容は中期講習とほとんど同じです。
また、講習の受講は、免許停止日数の半分が経過するまで受講できます。
例えば、免許停止日数が60日の場合なら30日、90日なら45日を経過するまでは、受講資格があります。
ご自身の予定を加味したうえで、早急に受講することをおすすめします。
軽い人身事故の場合は物損事故になる可能性がある
軽い人身事故を起こした場合は、警察が物損事故と判断する可能性があります。
交通事故の内容が人身事故であった場合、警察は詳しい調査や手続きを行う必要があります。
人身事故になると手続きや処理が増えることから、軽い人身事故に関しては手続きなどが簡易である物損事故で処理する場合があります。
被害者は「人身事故と物損事故のどちらとして処理するか」を決めることが可能です。
物損事故の場合は違反点数がつかないので点数は加算されません。当て逃げと判断された場合は7点加算されるので一発で免停になります。
当ててしまった自覚がある方は必ず警察に報告しましょう。
ただし物損事故でも被害者が体の不調を訴えれば人身事故に切り替えることもできます。
物損事故になったからといって被害者に謝らないなど不誠実な対応を取らずに、事故を起こしたことは相手にしっかり謝るようにしましょう。
人身事故で科される2つの処分
ここまでは違反点数や免停の対処方法について紹介してきました。
人身事故の場合は違反点数の加算以外にも処分を科される可能性があります。
人身事故の加害者が負う処分は以下の2つです。
| 受ける処分 | 受ける主なもの |
| 刑事処分 | ・懲役(刑務所で刑務作業を行うことが課せられる)
・禁錮(刑務所に入れられるが、刑務作業はない) ・罰金の支払い |
| 民事処分 | 損害賠償金の支払い |
では、以下で詳しく紹介していきます。
刑事処分
人身事故を起こして起訴された場合は刑事事件として扱われます。
刑事事件として立件されると、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法に基づき、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・殺人罪などの罪に問われ、懲役刑・罰金刑・禁固刑といった
刑罰が科されます。
交通事故に関する刑罰は、近年特に厳しくなりつつあります。著しいスピード超過や無免許運転などの危険な運転で被害者を死傷させてしまうと、危険運転致死傷罪に問われ、
以下のような懲役が科されるケースも考えられます。
- 被害者が死亡した場合:1年以上20年以下の懲役
- 被害者が負傷した場合:15年以下の懲役
さらに平成26年5月には、「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。
これによって、無免許運転や飲酒運転といった悪質な運転で被害者を死傷させた時の処罰がより厳しくなっています。
民事処分
民事処分とは、加害者が被害者の損害に合わせて損害賠償を支払うことを指します。
ここで言う損害とは、負傷・死亡させてしまった人物に対する損害や、車などを損壊させたことに対する損害を指します。
被害者に後遺障害が残った場合は、賠償金額が高くなる傾向にあります。
賠償金の金額は自動車損害賠償保障法や民法に基づき、被害者に対する損害賠償金の支払いを義務付けます。
民事処分によって支払う損害賠償金の中には、以下のようなものが含まれます。
- 被害者の治療費
- 車などの修理費
- 交通事故に遭わなかった場合に得られていたと考えられる利益
- 事故に遭ったことで受けた精神的苦痛への慰謝料
事故を起こして民事処分を受けた場合、運転者は自賠責保険によって損害賠償の一部を支払えます。
残りの金額については任意保険による保険金、もしくは実費で支払うこととなります。
まとめ
今回は、事故発生時の違反点数について解説してきました。
また、免停や点数がリセットされる期間なども合わせて解説してきました。
免許停止処分になった場合でも、短期・中期・長期講習を受けることで、大幅に免停期間を短縮することができます。
また、ご自身の累積点数や前回の違反からの期間を知りたい方は、証明書を発行することで確認が可能です。
事故車買取業者である「タウ」では、世界125ヵ国に及ぶ販売ネットワークを活かし、事故車両であっても高価買い取りさせていただきます。
3年連続業界№1の実績を誇る弊社が、責任を持って無料査定いたします。
全国どこでも、24時間、年中無休で受付しております。
損傷が激しいお車でも、最短で翌日にはお引き取りできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 小池 一敏
小池 一敏
事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。